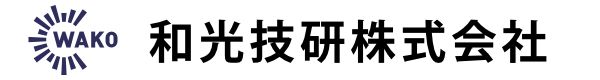令和7年6月20日(金)に「令和7年度 和光技研技術発表会」を開催いたしました。
和光技研では、業務上の工夫や技術的検討、専門的な知見や経験を共有する場として毎年技術発表会を開催しており、今年で第26回目となります。
■特別講演
◆ 真の知識は理解と経験から
北海道大学大学院 工学研究院 土木工学部門 教授 渡部 要一様
北海道大学や港湾空港技術研究所での経験に基づき、各研究テーマの概要や今後の技術展望、さらに見聞を広げることの意義などについてご講演頂きました。

■技術テーマ部門
機能保全計画を踏まえた排水路補修工事の設計業務
水工部 吉田 正志
当該排水路は供用開始40年以上が経過し、護岸施設等の老朽化に起因した機能低下により冠水被害が度々発生していた。このため、農業水路等長寿命化・防災減災事業により機能回復を目的とした排水路補修工事を計画、令和5年度に機能保全計画の策定、令和6年度に排水路補修区間の詳細設計を実施した。
本発表では、機能保全計画策定から詳細設計に至るまでの業務の流れや検討事項について、特に苦慮した点を踏まえながら発表した。
液状化検討の応用理学的な対応事例
道路構造部 佐藤 匠
道東の太平洋沿岸の町では、千島海溝地震防災対策の津波防災として、人道橋を含む避難路整備を計画していた。橋の基礎形式は、当初、周辺の既往ボーリング調査から浅部の砂層(N値50以上)を支持層とする杭基礎としていた。しかし、詳細調査を行ったところ、砂層の層厚は5m程度で、下位にN値20未満の相対的弱層が厚く分布してることが明かになり、設計上の問題(支持力不足)が懸念された。
本発表では、相対的弱層の液状化について、応用理学的なアプローチで解決を試みた事例を紹介した。
頻発する洪水被害と河川環境のバランスに配慮した農地河川における流域一体の改修事例の紹介
河川環境部 髙井 孝浩
U川では、頻発する洪水被害に対し、利水ダムへの洪水調節機能の確保と、ダム下流の河道掘削・堤防の整備等、流域一体の整備が進められている。また、地域振興への配慮から、地域のシンボルとなっている絶滅危惧種イトウを頂点とした生態系ネットワークの保全が最重要テーマとなっている。
これらの背景のもと、各関係機関との現地意見交換を重ね、ダム下流の河道において掘削形状を工夫して湿地・ワンドの創出を意図した計画・施工が進められている。本発表では、計画立案から設計・施工、施工後のモニタリング調査結果について報告した。
■自由テーマ部門
自由テーマ部門では、老若男女問わず、業務改善に繋がる取組や創意工夫などが発表されました。
| SLAMハンディスキャナの実力とは?点群データで見る比較検証 | 株式会社ゆほびか 矢尾達也 |
| 高精度3次元デジカメ「Leica3Dイメジャ BLK3D」の導入と調査業務への活用 | 建築補償部 名古屋 龍弥 |
| 営業部の業務内容と電子化への対応について | 営業部 太田香名 |
| CO2削減に関する取り組みの結果報告と今後の目標について | 技術管理部 佐々木 真歩 |
■社内技術士部門
道路構造部 長谷川技術士より、「技術者倫理」についての講演がありました。
今年の最優秀発表者は、道路構造部の佐藤匠さんが選ばれました。
今回も、発表や質疑応答を通じて普段あまり接しない部門の取り組みや知見を共有することができ、発表を行った社員は勿論、質疑応答に参加した社員にも非常に有意義な時間となりました。